筋膜リリースの効果とは?痛みが軽減する?|山口県下関市のだて整形外科リハビリテーションクリニック
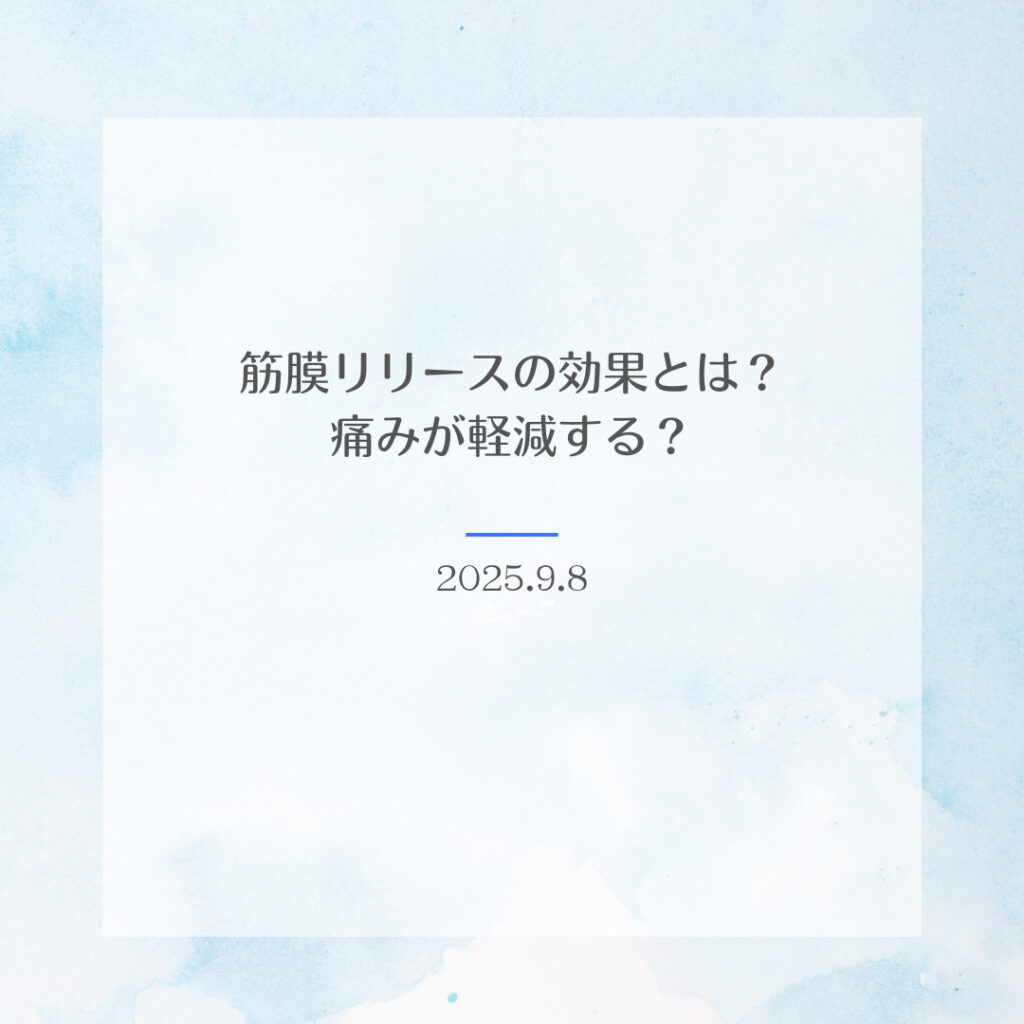
筋膜リリースは、スポーツ選手からデスクワーク中心の方まで、幅広い層に注目されている施術方法です。筋膜とは、筋肉や内臓を包み込み、体全体をつなぐ薄い膜のことで、この膜が硬くなったり癒着したりすると、肩こりや腰痛、関節の可動域制限など、さまざまな不調を引き起こす要因になります。日常生活で同じ姿勢を長時間続けたり、運動不足が続いたりすると筋膜がこわばり、血流やリンパの流れが滞りやすくなります。
筋膜リリースは、この硬くなった筋膜をやさしく伸ばし、柔軟性を回復させることで、コリや痛みの軽減、姿勢の改善、動きやすい身体づくりをサポートします。リハビリやスポーツコンディショニングの現場でも活用されており、整形外科や治療院での治療プランの一部として取り入れられるケースも増えています。
本記事では、「筋膜リリースの基本」から「筋膜リリースの具体的な効果」についてご紹介します。
筋膜リリースとは何か
筋膜リリースは、筋肉や内臓を包む薄い膜「筋膜」にアプローチして柔軟性を回復させる手技療法です。筋膜は全身をネットワークのようにつなぎ、姿勢や動作の安定性を保つ重要な役割を果たします。しかし、長時間の同じ姿勢や偏った動き、ストレスなどの影響で筋膜は硬くなりやすく、癒着すると血流やリンパの流れが滞ります。その結果、肩こりや腰痛、関節の可動域制限といった不調が起こります。筋膜リリースでは、この硬くなった筋膜をじっくりと伸ばし、柔らかくすることで、痛みや動きにくさの改善を目指します。
筋膜の役割と硬くなる原因
筋膜は「第二の骨格」とも呼ばれ、骨や筋肉を正しい位置に保ち、力の伝達をスムーズにします。加えて、衝撃を吸収し、体を守るクッションのような機能も持っています。しかし、運動不足や姿勢の乱れ、過度なトレーニングによる負荷、外傷などで筋膜は簡単に硬化します。さらに、精神的ストレスによる交感神経の緊張が筋膜の収縮を招くこともあります。
筋膜が硬くなると、その部分だけでなく全身のバランスに影響し、遠く離れた部位にも痛みや違和感を生じることがあります。このため、症状の根本改善には筋膜全体へのアプローチが欠かせません。
筋膜リリースで期待できる効果
筋膜リリースの最大の効果は、コリや痛みの軽減です。筋膜がほぐれることで血流やリンパの流れが改善し、老廃物が排出されやすくなります。その結果、酸素や栄養素が筋肉に届きやすくなり、回復力も高まります。さらに、関節や筋肉の可動域が広がることで、動作の効率が上がり、怪我の予防にもつながります。
スポーツ選手にとってはパフォーマンス向上、デスクワーカーにとっては姿勢改善や肩こり・腰痛の緩和が期待できます。また、筋膜リリースはリラクゼーション効果も高く、心身のストレス軽減にも役立つとされています。

痛み軽減のメカニズム
筋膜リリースによる痛みの軽減は、物理的な緊張緩和と神経の過敏状態の改善によって起こります。硬く縮んだ筋膜は内部の神経を圧迫し、痛みを引き起こす物質(ブラジキニンやプロスタグランジン)を放出します。筋膜リリースで筋膜を伸ばすと、こうした化学物質の蓄積が減少し、神経圧迫が和らぎます。また、筋膜に存在する感覚受容器が適度な刺激を受けることで、脳が痛みを抑制する信号を送りやすくなります。これにより慢性的な痛みが軽減され、動きやすさが向上します。
筋膜リリースの方法と施術例
筋膜リリースには手技による方法と器具を用いる方法があります。手技では、セラピストや理学療法士が手のひらや前腕、指を使ってゆっくりと圧をかけ、筋膜を伸ばします。器具を使う場合は、フォームローラーやボール状のツールで自重を利用しながら特定部位に圧を加えます。整形外科やリハビリ施設では、症状や目的に応じて施術部位や圧の強さを調整し、筋膜全体をバランスよく解放していきます。特に慢性的な肩こりや腰痛、スポーツによる筋疲労には、定期的な施術で効果が持続しやすくなります。
自宅でできるセルフ筋膜リリース
筋膜リリースは専門家による施術が効果的ですが、自宅でのセルフケアも可能です。代表的なのはフォームローラーを使った方法で、ふくらはぎ、太もも、背中などをゆっくりと転がすように刺激します。ポイントは、強く押しすぎず、呼吸を止めないことです。痛みがある部分を無理に長時間刺激すると逆効果になる場合もあるため、1か所につき30秒〜1分程度を目安に行います。また、日常生活での姿勢改善やストレッチと組み合わせることで、筋膜の柔軟性を長く保つことができます。

筋膜リリースを受ける際の注意点と適応範囲
筋膜リリースは多くの人に有効ですが、すべての症状に適しているわけではありません。骨折や炎症、深部静脈血栓症、皮膚感染などのある場合は避ける必要があります。また、高血圧や心疾患を抱えている方は、医師に相談してから行うことが大切です。施術を受ける際は、経験豊富な専門家に依頼し、自分の症状や体調を正確に伝えることが安全性を高めます。継続的に受けることで効果が積み重なりやすいため、症状の経過を記録しながら進めるとより効果的です。
監修者情報
日本整形外科学会専門医 伊達 亮(だて整形外科リハビリテーションクリニック 院長)
福岡大学医学部医学科を卒業後、山口大学医学部付属病院整形外科・麻酔科での経験を経て現職に至る。日本整形外科学会専門医 、日本骨粗鬆症学会専門医 、日本リハビリテーション医学会専門医 など多岐にわたる専門医資格を保持し、地域の「寝たきりゼロ」をミッションに掲げ、骨粗しょう症の早期発見・早期治療、および運動器リハビリによる転倒予防に尽力している。
