骨折予防のための骨粗鬆症診療~みんなで取り組めば骨折は減らせる~
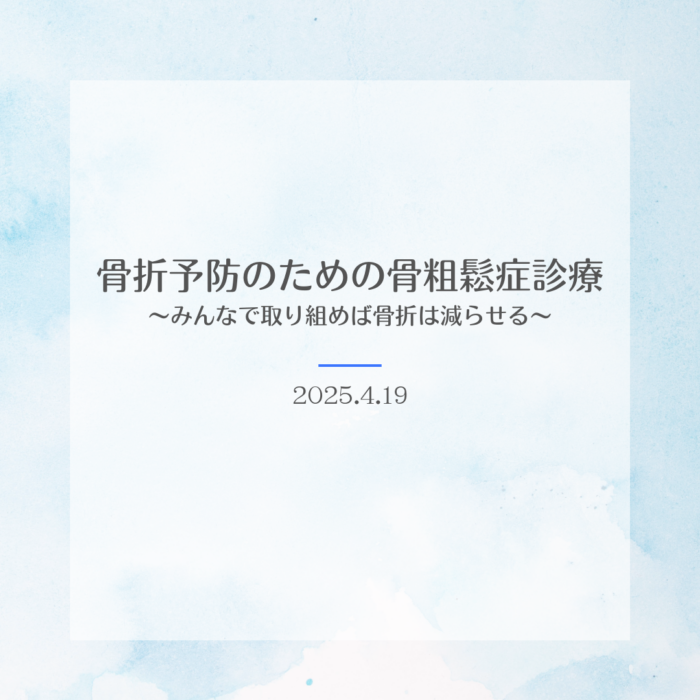
【寝たきりゼロを目指す!下関で取り組む最新の骨粗鬆症診療】
こんにちは。だて整形外科リハビリテーションクリニック院長の伊達亮です。
2025年4月19日、TKP博多駅前シティセンターで開催された「第403回福岡臨床整形外科医会教育研修会」にて、骨粗鬆症の診断と治療について学ぶ機会をいただきました。産業医科大学医学部整形外科学講師・塚本学先生によるご講演「骨折予防のための骨粗鬆症診療~みんなで取り組めば骨折は減らせる~」を拝聴し、多くの示唆を得ることができました。今回はその内容を、下関地域の皆さまにもわかりやすくお伝えしたいと思います。
■ 骨粗鬆症とは? 骨粗鬆症は骨の強度が低下し、骨折しやすくなる病気です。特に高齢の方では、わずかな転倒でも骨折してしまうことがあります。骨折の既往がある方や、骨密度が低い方は、骨折のリスクが特に高まります。診断には、骨密度測定だけでなく、既往骨折の有無や骨代謝マーカーの測定、脊椎のX線評価も重要です。
■ 骨折のリスクと早期対応の重要性 脆弱性骨折後2年以内は、最も再骨折のリスクが高い期間です。特に脊椎や大腿骨近位部の骨折は要注意。初回骨折が起きた時点で、骨の強度はすでに大きく低下しているため、すぐに治療を開始することが望まれます。
■ 骨の構造とリモデリングの理解
骨には皮質骨(硬い骨)と海綿骨(網のような骨)の2種類があります。骨は常に「骨リモデリング」と呼ばれる入れ替えを行っており、年齢とともに吸収が進み、形成が追いつかなくなると骨量が減少します。
■ 最新の治療戦略:骨吸収抑制と骨形成促進
骨粗鬆症治療には、骨を壊すのを防ぐ「骨吸収抑制剤」と、骨を作る「骨形成促進剤」があります。
骨吸収抑制剤:デノスマブ(半年に1回注射)
骨形成促進剤:アバロパラチドやテリパラチド
アバロパラチドやテリパラチドは骨密度の改善に非常に有効で、その後の「逐次療法(アレンドロン酸など)」によって追加骨折の予防効果がさらに高まります。
■ デノスマブの継続投与の重要性 デノスマブは非常に効果的ですが、継続が何より重要です。6か月に一度の投与を守ることが骨折予防には欠かせません。8か月以上空くとかえって骨折リスクが急増します。
■ COPDと骨粗鬆症の関連性
慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者では、酸化ストレスやミトコンドリア機能障害が骨粗鬆症のリスク要因として注目されています。抗酸化剤の活用によって、骨・筋機能の改善が見込まれる可能性も示唆されました。
■ 下関地域での今後の取り組み
当院では、骨粗鬆症の予防と治療に積極的に取り組んでいます。特に以下のような体制を整えています。
骨密度検査の迅速な実施(DXA法)
デノスマブ等の注射治療の継続管理
骨折予防のための生活指導
高リスク患者へのフォロー体制強化
■ まとめ
骨粗鬆症は「骨折してからでは遅い」病気です。地域の皆さまが健康な骨を維持し、寝たきりを防ぐために、早期の診断と継続的な治療を行うことがとても大切です。
今後も当院では、「地域で一番信頼される整形外科クリニック」として、科学的根拠に基づいた診療を提供し、骨粗鬆症による骨折ゼロを目指します。
下関で整形外科・骨粗鬆症治療をお考えの方は、ぜひ当院にご相談ください。
だて整形外科リハビリテーションクリニック
院長 伊達亮
